樫本大進&ラファウ・ブレハッチ デュオ・リサイタル
ご紹介
新世代を牽引する若きリーダー2人の共演が実現
.jpeg@@6b079c896e3f7efe231a714825dcede4.jpeg)
昨年後半でもっとも心に残ったコンサートのひとつがこれだった。リリシズムの極致をいく“ショパン弾き”として絶大な人気を誇るブレハッチ。そしてベルリン・フィルの第1コンサートマスターにしてソロに室内楽と八面六臂の活躍をとげ、いまやヴァイオリン界の若きリーダーといっても過言でない頼もしい樫本大進の初顔合わせとなるデュオだ。会場のサントリーホール大ホールはもちろん満席(2024年12月19日)。
プログラムの構成が凝っていて、前半がモーツァルトの ハ長調K.296 とベートーヴェンの第7番ハ短調op.30-2 のヴァイオリン・ソナタ。後半は武満徹「悲歌(エレジー)をはさんで、ドビッシュ―(イ短調)とフランク(イ長調)のヴァイオリン・ソナタ。前半がドイツ系、後半にフランス系の音楽をまとめたかたち。
ピアノが活躍するモーツァルトのソナタから若き名称2人の輝きと熟練性とで一瞬のうちに場内をモーツァルトの快活な世界へと引きずり込む。両端楽章の爽快なテンポ、中間楽章アンダンテ・ソステヌートでのアリアのような優美さ(それも過剰でなく)は特筆される。
ブレハッチは第1楽章アレグロ・ヴィヴィーチェのコーダの音型を前打音を含む1小節を16分音符4つという珍しい解釈で弾いていた。同じモーツァルトの行進曲のテーマと同じ弾き方である。一方の樫本は通常通りだったので2人の違いが出て面白かった。またブレハッチのモーツァルトの音色処理の巧みさに惹かれた。基本ノンレガートなのだがペダルの微妙な使用により、しっとり感があり乾いた無表情な音質ではなかったこと。音階的なフレーズや細かなパッセージでもこれは一貫し(音量の幅も最後まで一定)軽やかでいて奥深い音楽を紡ぎあげていた。録音やYoutubeで彼のモーツァルトを聴くことができるがこの日聴いた演奏はこれまでにないものだった。
.jpeg@@1df74e6b7f5b76d5dfff83b02c5e9360.jpeg)
一方の樫本のヴァイオリンも気持ちよいほど高音の伸びとレガートが美しく、彼の大きな武器である多彩な表情づけが聴きもの。ブレハッチの精緻なピアニズムにより樫本の資質が際だつこととなる。ベートーヴェンも樫本とブレハッチはモーツァルトとほぼ同様のバランス感で音楽に向かい合っており、「ベートーヴェンのハ短調」だからと言って過度にアパッショナートな表現にならず軽やかな中に暗い緊張感を孕ませ、品格のある大人の音楽を作り出した。リズム感が際だつ第3楽章スケルツォはアンコールでも弾かれたことでも分かる通り会心のベートーヴェンだった。
武満徹の「悲歌」ではヴァイオリンの重いテヌートと透明感に溢れるピアノのトーンとが見事にブレンドされ、聴衆を前半の律動間溢れる世界と違う次元へと誘っていく。この空気感はドビュッシーでも生かされ、やわらかに絡み合う弦とピアノが官能的な空間を生み出す。音量的な起伏よりもドビッシュ―のもつ多様な色彩感の表出をめざしていて成功していた。武満とドビュッシーの音楽の近似性はよく指摘されるところだが、あらためて連続して聴いてみると相違が分かって面白いものだ。ここでもブレハッチのペダリングが光る。
最後のフランクでは2人の主張がもっとも発揮されていて、柔軟なフレージングと中庸を行くゆったりとした歌、そして決然としたフォルテ!といっても神経のゆきとどいた美しいトゥッティである。終楽章でのしなやかなカノンのやりとりも絶妙。いつまでも聴いていたい演奏だった。
.jpeg@@ac22f5f6377180ec9dc42eefe2ffdecb.jpeg)
樫本大進は2025年6月にアレッシオ・バックス(ピアノ)とのコンビで来日しデュオを披露するいことが決定している。
(文:TS)




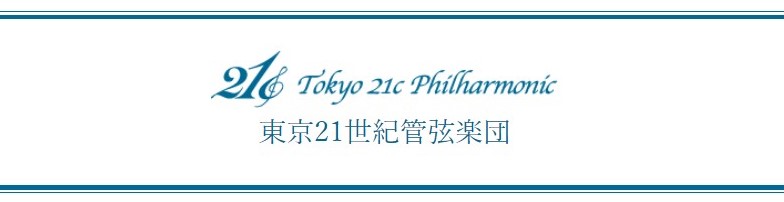
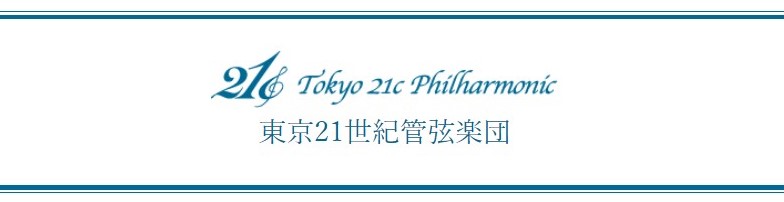



%20Marco%20Borgreve-Ca2.jpg%40%40702706ba0036f14deecb3a4c0a9910ef.jpg&w=3840&q=75)

.JPG%40%406c9a39650ef694fcfba43d1aec1175e7.JPG&w=3840&q=10)
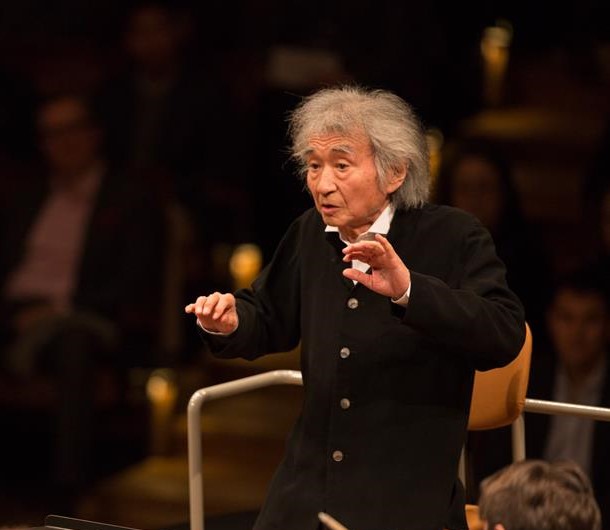
%20Marco%20Borgreve-1.jpeg%40%40db78161701210c309182abb229947728.jpeg&w=3840&q=10)

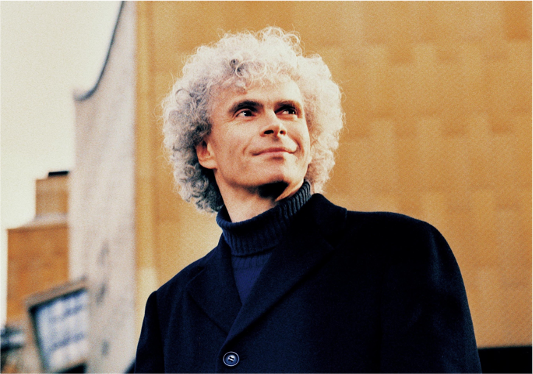



%20Marco%20Borgreve-1.jpeg%40%40db78161701210c309182abb229947728.jpeg&w=640&q=75)