ジャンル
作曲家
(2024年02月29日)
来日レポ:ラファウ・ブレハッチ リサイタル
昨年にひき続き内外のピアニストたちの優れたコンサートが相次ぐ中、ラファウ・ブレハッチのリサイタルが行われ満員となったギャラリーを魅了した。
2月22日、東京オペラシティコンサートホールでの模様をレポート(当公演以外に所沢市民文化センター ミューズ、大阪 ザ・シンフォニーホール、ミューザ川崎シンフォニーホール、横浜市青葉区民文化センター・フィリアホール、長崎 とぎつかカナリーホールで演奏)。

聞き手一人ひとりに語りかけるようなマズルカ
4つのマズルカop.41、3つのマズルカop.50、3つのマズルカop.56、3つのマズルカop.63が前半。休憩をはさんでピアノ・ソナタ第2番op.35「葬送」、そして4つのマズルカop.24というオール・ショパン・プロが組まれた。みてお分かりの通り一晩でマズルカをこれほど並べた例は珍しく、“ショパン弾き”としてのブレハッチの魅力を再確認する演奏会となった。ブレハッチは言うまでもなく第15回ショパン国際ピアノコンクールの覇者として名高いが、ポーランド人のピアニストとしてコンクール後にドイツ・グラモフォン・レーベルと専属契約をを交わしたのは、かのクリスチャン・ツィメルマン(第10回優勝)以来のこと。
ポロネーズ賞、コンチェルト賞、ソナタ賞(ツィメルマンによってこの回から初めて制定された)、オーディエンス賞、そしてマズルカ賞と、すべての賞を制覇して優勝して以来、その名をとどろかせ日本でも高い人気を誇ってきたが、彼のステージは常に外面的な派手さと無縁で、作品の芸術性を声高にでなく表現する。内向的なキャラクターの持ち主ということも相まってショパンの内奥を聴きて一人ひとりに語りかける、そんなインティメイトな姿勢は一貫している。
マズルカは全体的にテンションを抑えたテンポ設定をとり、跳ねるような付点音符の強調もなく、ひたすら柔らかな旋律線とショパン特有の微妙な和声感の移り変わりが印象的で、その美しさは、ほぼずっと踏まれていたペダルの巧な効果によって、場内に音色のグラデーションを魔法のように醸し出した。

気品に満ちたロマン性
後半は発表されていた曲順が変更となり、ソナタから開始されたが、ここではマズルカとは打って変わり緊迫した世界と陰影観が表されるのだが、そのロマン性はけっしてどぎつくなく、デリカシーを伴いこれみよがしな表現に陥らない。有名な第三楽章「葬送行進曲」も極度の弱音を使用し不気味な味わいを醸し出していた。変ニ長調の中間部ではあのシンプルで優しい旋律をまるで天国からの救いのように奏し、この日の白眉となった。休止を置かずに弾かれた終楽章も徹底的にコントロールされた中音量のなかで一寸の乱れもなく──しかも曲の前衛性をおろそかにせずに──鮮やかに締めくくった。
至難なパッセージを大音量でバリバリと弾くヴィルトーゾたちの弾くショパンに慣れてしまった向きにはかなり新鮮に聴こえ、そしてショパンの繊細な味わいというものを再確認させたコンサートになったと思う。鳴りやまぬ拍手に応えてのアンコールはop.56からの第2番と第3番。そして「軍隊ポロネーズ」。荒々しさでなく高貴で心に染みるポロネーズだった。

12月には樫本大進との初共演も実現!
終演後にはCDを購入したお客さんに向けてのサイン会も開かれ、長蛇の列がオペラシティのロビーをいっぱいにした。コロナ禍後に初めて目にする光景だった。今年の12月にブレハッチは再来日を果たし、ヴァイオリンの樫本大進とのデュオコンサートが開催されることも発表されすでに大きな話題となっている。モーツァルト:K.296、ベートーヴェン:第7番、ドビュッシー、フランクのヴァイオリン・ソナタ、武満徹「悲歌」が取り上げられる予定だ。(文:T・S)
※写真はいずれも2月20日のミューザ川崎シンフォニーホール公演での撮影。




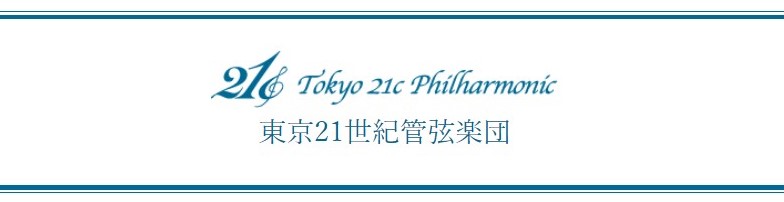
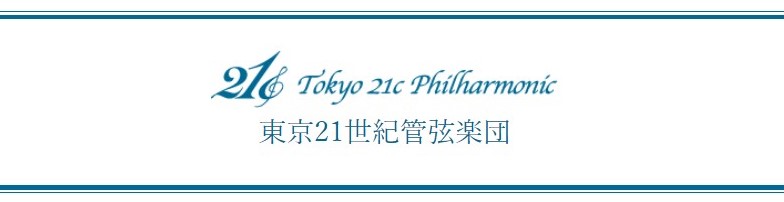



%20Marco%20Borgreve-Ca2.jpg%40%40702706ba0036f14deecb3a4c0a9910ef.jpg&w=3840&q=75)





