ジャンル
作曲家
(2024年05月16日)
来日レポ:グリゴリアン・ソプラノ・コンサート
話題のディーヴァによるソロ・コンサートが実現!

世界の主要歌劇場から熱い視線を浴びるリトアニア出身のソプラノ、グリゴリアン。一昨年、ミューザ川崎での《サロメ》(ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団)での名唱は記憶に新しいところだが、こんどは単独での来日を果たし初日にはチャイコフスキー、プッチ―ニなどロマン派名作オペラからのアリアを披露した(Aプロ/5月15日、東京文化会館大ホール)。共演はカレン・ドゥルガリアン指揮の東京フィルハーモニー交響楽団。
ノースリーブでスリット入りの黒いドレスで登場したグリゴリアン、歌うまえに指揮者やオーケストラにも拍手を送るなど品のあるマナーには好感がもてる。キリっとした雰囲気に柔らかさも漂わせる。
ルサルカやタチヤーナ、リーザの憧れと哀しみがリアルに迫る
オープニングは没後120年のドヴォルザーク《ルサルカ》。短い序曲の後、とくに身構えることもなく〈月に寄せる歌〉を歌い始めた。グリゴリアンの声質はやや暗くシックな音色を帯びるがその音色のまま高音にのぼっていくのはスリリングであり美しい瞬間だった。彼女の歌は感情そのもので(しかも過剰でない)、四角四面の4小節単位の譜面から微妙にはみ出すような柔軟な表現は聴くものを酔わせる。
チャイコフスキーでは「イアン・サマーリンの思い出」が管弦楽で奏されたあと、《エフゲニー・オネーギン》から〈手紙の場〉と「ポロネーズ」。夢見がちで初心な少女の心情というよりも、すでに成熟したタチヤーナが自分の初恋を回想する…そんな情景を表出するかのようで、艶やかさと知性(と品格?)を漂わせ興味深かった。これについては本人の解釈を訊いてみたいところ。同じ作曲家の《スペードの女王》でリーザが絶望の中で歌う〈ああ、悲しみで疲れ切ってしまった〉もリアルで等身大のキャラクターの情感がひしひしと伝わり、
前半最後は、アルメニア出身のグリゴリアンの愛唱曲というアルメン・ティグラニアン(1879~1950)のオペラ《アヌッシュ》からの題名役が歌う〈かつて柳の木があった〉というアリアで、しっとりとしたエキゾチシズムに溢れる魅力的な旋律とハーモニーが印象的でとても面白く引き込まれた。
ここまでほぼフラット系(=♭系)の調の楽曲でまとめたプログラミングの妙も特筆もの。

蝶々さんやトスカの心情をリアルに歌いきる
後半は没後100年のプッチーニばかりでまとめられた。ここからグリゴリアンはリリコの本領を発揮。本日の演目のなかでもっともふさわしいと思える《トゥーランドット》のリュ―の〈氷のような姫君の心も〉での限界状態での訴え、そして《マノン・レスコー》の〈捨てられて、ひとり寂しく〉と《蝶々夫人》から〈ある晴れた日に〉ともに主人公の孤独感がに自在に描かれた。ドラマティコのソプラノにありがちな圧迫感のある歌唱とはまったく異なるリアルな女性心理の表現をめざしているようで、強弱やブレスなど絶妙しかも役柄の存在感を感じさせ場内を魅了した。

オーケストラの演奏による「菊」の後に歌われた《ジャンニ・スキッキ〉での優しさにあふれた〈私のお父さま〉でも芸風の広さを披露、グリゴリアンの底知れぬ才能と力量とを見せつけた。アンコールは《トスカ》の〈歌に生き、愛に生き〉で場内は熱狂、日本でも間違いなくファンを増やしたはず。今後の活動がますます注目される。(文:T・S)
©Kiyonori Hasegawa
アズミク・グリゴリアンが聴けるコンサート
Bプロ 2024年5月17日(金)19:00 東京文化会館(大)




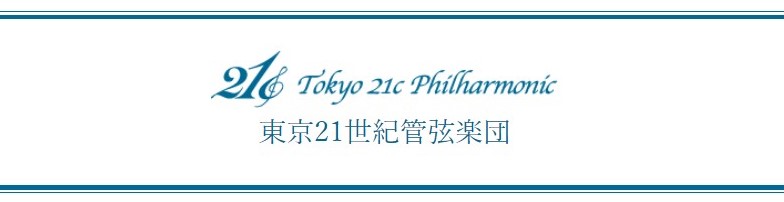
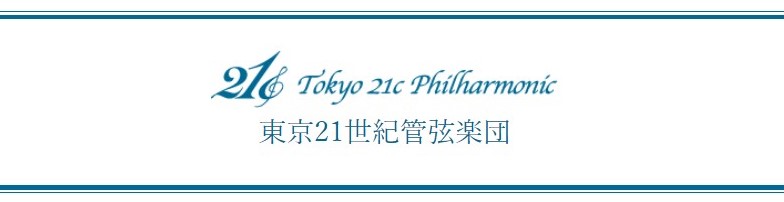



%20Marco%20Borgreve-Ca2.jpg%40%40702706ba0036f14deecb3a4c0a9910ef.jpg&w=3840&q=75)





